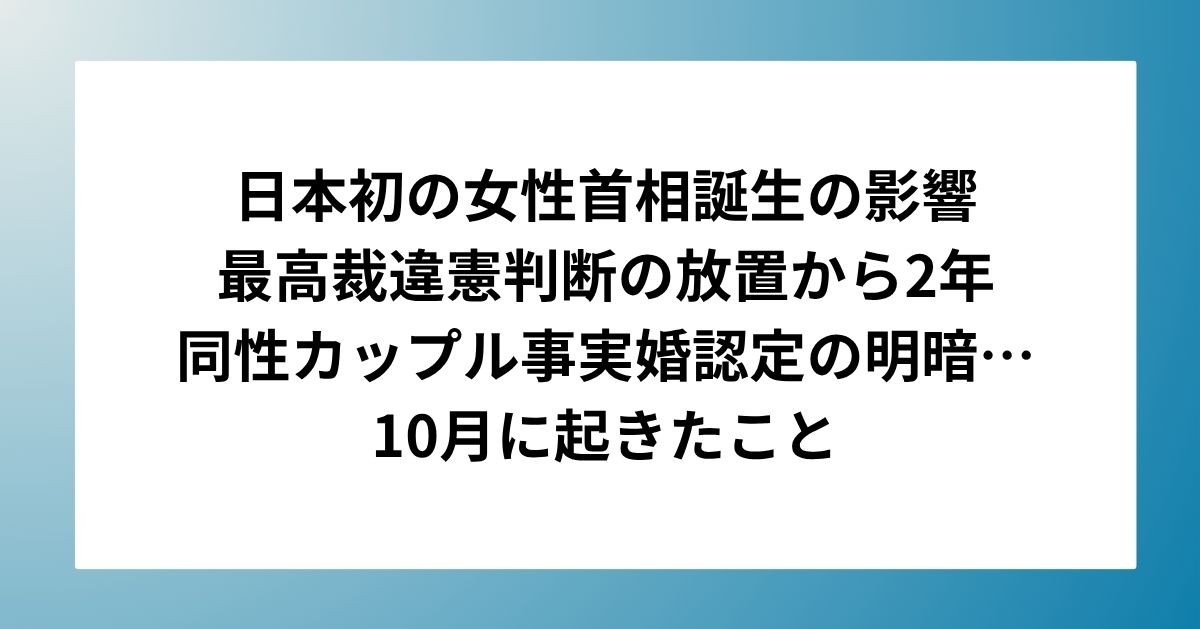司法による「意志をもった差別」東京高裁判決の5つの問題点
28日、婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京2次の高裁判決があった。
これまで5つの高裁判決で憲法違反の判断が下されているなか、同種訴訟の最後の高裁判決である東京高裁は唯一、合憲と判断した。
しかし、その内容は当事者の困難に向き合うこともなく、同性カップルを排除する理由について正面から論じることから逃げ、論理は破綻し、司法の役割をも放棄するものだった。それだけでなく、意志を持って「性的マイノリティを差別したい」と、そういう内容の判決だったと言える。
判決要旨から、その問題点について考えたい
①「結婚とは国家のために子を産み育てるための制度で、それ以外の家族は守らなくていい」という姿勢
今回の判決でもっとも劣悪だと感じたのは、東京高裁が憲法の前文まで持ち出し、「結婚とは国家のために夫婦が子どもを産み育てるための制度」であるかのような主張をしている点だ。
東京高裁は、結婚とは「夫婦とその間の子」の関係を想定した制度だと述べている。ただ、近年は「夫婦とその子ども」という形だけが「家族」というわけではなくなってきているとも言う。
ではなぜ「結婚は夫婦が子どもを産み育てるための制度」だと言えるのか。東京高裁は「生まれる子の側からみれば、100%近くが夫婦の間の子として出生して養育」され、「そのような国民が、なお全体の4分の1に及ぶ」ことや、未婚率が高くなっていても、子どもは結婚した夫婦のもと生まれてくる事実があるから、結婚とは夫婦と子どものための制度なのだという。
これは法律上の同性カップルだけに限らない差別的な考えだ。「100%近く」という非常に雑で暴力的な物言いが出てきているが、異性カップルであっても、離婚後の連れ子で親同士は結婚していないことだってある。里親や養子縁組で子を育てる人もいる。こうした人たちも「結婚すべきではない」ということだろうか。
結婚した夫婦と子どもが、全体の4分の1という点を主張しているが、客観的にみてこれは多数ではなく、これをもって同性カップルの排除を正当化する理由にはまったくならないだろう。異性カップルは子を持たない・持てなくても結婚できるという矛盾については答えておらず、論理があまりに稚拙だ。そもそも異性カップルも含めて、婚姻は共同生活の保護であり、子どもを持つかどうかは結婚の要件ではないのが実態だ。
東京高裁はさらに、憲法の前文まで持ち出して差別を助長する。
判決では、憲法は「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」とうたっており「国家は、世代を超えて維持されることを前提」とし、「男女の性的結合関係による子の生殖」が、国民社会を維持する上で「通常の方法」なのだと言う。
つまるところ、「国家のために男女は子を産め、そのための結婚制度だ。そこに貢献できない関係は家族として認めない」と、憲法の前文を持ち出して主張しているということだろう。
裁判官にとって、法律上の同性カップルは、憲法の前文にある「われらとわれらの子孫のために」の「われら」にも「子孫」にも含まれないのだろうか。実際には同性カップルで子を産み育てている人はすでに存在する点からも、この論理がいかにおかしいかがわかるが、たとえ子を持たない場合でも、国家の維持に貢献できない人を守る必要はない、と言いたいのだろうか。杉田水脈氏の「LGBTに生産性はない」という言説と何が違うのだろうか。
判決が引用している憲法前文の「(中略)」とされた箇所のなかには「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」と書かれている。つまり前文は、われらとわれらの子孫のために、自由のもたらす恵沢を確保することなどを求めているのであって、直接的に「子孫繁栄」を求めることを目的とした文言ではないことは明らかだ。憲法の番人であるはずの裁判官が、基本的人権を保障するはずの憲法について、非常に恣意的かつ差別的な読み方で、マイノリティの人権を制限するために使ってしまっている。
憲法24条の趣旨は、「家父長制からの脱却」だ。結婚は、国家や家などの集団のために、家長である父親が決めるものではなく、当事者どうしの意志で結婚について決められるという意図でつくられた。裁判官はこうした憲法の趣旨に反し、旧来の家父長制に基づき、強い意志をもって“ふつうの家族”に当てはまらない人たちを差別し、排除しようとしているかがありありと伝わってくる。こんな考え方の人々が、少数者の権利を擁護するはずの裁判官という立場にいることに絶望してしまう。
さらに東京高裁は、だれもそんなことを主張していないのに、もし「夫婦とその子ども」の関係を保護するという婚姻制度の規定が存在しなければ、「誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」などと述べる。法律上同性のカップルの結婚を認めると、結婚制度がなくなり誰も結婚ができなくなるかのような意味のわからない論理だろう。
②具体的な生活の困難は無視し、詭弁ばかりで逃げる論理
法律上同性のカップルが家族として守られる制度がないことが、「法の下の平等」を定める憲法14条に違反するかという点について、東京高裁は、家族に関する制度については国会に裁量があり、海外では制度がある国もない国もあることなどから、制度が存在しないことがただちに憲法に違反するわけではないと述べた。
さらに、家族に関する法制度は、「制度に差別があってはならないが、差別を解消することをその制度本来の目的とするものではない」などという。続けて「性自認等の多様性に対する国民の理解不足を解消する方策も、家族に関する法制度の創設だけではなく、例えば、差別を禁止する明示的な法律を立法するという方策もあり得る」と述べる。
いずれも、法律上同性のカップルの生活の困難にまったく向き合わず、なぜ制度によって守られないことを正当化できるのかという理由に、正面から答えられていない。
具体的な生活の困難や、権利の不平等があることは明白で、制度的に国は何の手立てもしていないのは明らかな差別的取扱いだ。裁判では、そうした生活上の困難をめぐる対応について、異性カップルと同性カップルで差を設けることに合理性があるかが問われている。それにもかかわらず、制度にはいろいろなものがあり、他の国では制度がある国もない国もあるから差別ではないという、そんな言い逃れのような幼稚な論理でまかりとおるはずがない。
「家族に関する法制度は差別を解消することが目的ではない」という点も詭弁だ。たとえ差別禁止法ができても、同性カップルの結婚自体が認められるわけではなく、論点ずらしでしかない。
憲法14条は「法の下の平等」を保障しているが、判決では終始、実際に目の前にいる当事者の存在と、その生活実態をことごとく無視している。異性カップルと同性カップルの間にある具体的な不平等について向き合うこともなく、「結婚とは男女が子を産み育てるためのの制度だから」ということだけを述べている。巧妙に、排除ありきの言い訳ばかりが並び、正面から論じることから逃げている。
③「事実婚で認められてきているし、いいでしょう」という差別
東京高裁の判決では、前半で、法律上同性のカップルについて「事実婚とでも呼ぶべき」といい、しかし異性の事実婚とは「異なる状況に置かれている」と述べ、「重要な法的利益が十分に尊重されているとは評し難い」と現状の問題性を認識している。
それにもかかわらず、後半では、法律上同性のカップルは「事実婚として保護されている」などという。さらに「関連する法制度の趣旨に即して個別に適用ないし類推適用を受ける」ことができ、扶養や財産分与、相続など、「婚姻の基本的かつ重要な法的効果の一部」については「契約で代替する方法がある」と述べている。
前半では「守られていない」といい、後半は「守られている」と矛盾した論理を展開する。これはつまり「事実婚である程度認められているから、それでいいでしょう」という趣旨だろう。
確かに政府は今年、33の法令で「同性カップルも事実婚に該当し得る」という方針を発表している。しかし残り120の法令では排除されたままだ。当事者の生活にとって最も重要な社会保障に関する制度をはじめ、ほとんどの制度で事実婚として扱われていない。
そもそも「同性婚」が認められていないから、当事者の生活を守るために、一部の制度だけでも事実婚として保障されるよう求めているにもかかわらず、「一部で認められてきているから結婚できなくても良いでしょう」というのは詭弁でしかない。
さらに、事実婚として認められるようになったからといって、相続などで異性カップルの結婚と同じように平等な権利を得られるわけではない。この点について、東京高裁は「契約で代替できる方法がある」というが、異性カップルは婚姻届を出すだけで権利が得られる一方、同性カップルは費用をかけて契約をして、それでも異性と同じような権利を得られるわけではない。どこまでいっても「平等」は実現しないのだ。東京高裁は歴然と横たわる差別を意図的に肯定しているとしか言えない。
判決では、法律上同性のカップルについて「法律による公証とは異なる」ものの、地方自治体のパートナーシップ制度の人口カバー率が9割にのぼり、企業では同性カップルも異性間と同じようにサポートを受けられるようになってきているとし、すでに同性カップルは社会的に承認されているかのような論理を展開している。
「同性婚」が認められていないから、法的効果がなくても自治体や企業ができる範囲の手立てを講じている。これをもって「社会的承認が得られている」とするのは言語道断だ。
そもそも社会的承認という名のマジョリティからの"許可"によって、家族かどうかを認めるかを判断する考え方自体が問題だ。このロジックは、一方では「社会的承認がないから同性カップルを家族とは認められない」と言われ、もう一方では「すでに社会的承認が得られているから認めなくても良い」かのように言われるなど、あまりに都合のよい論理として用いられている。
判決ではさらに、トランスジェンダーについて「特例法による法律上の性別の変更を経て、法律婚を選択することができる」という点も述べている。例えばトランス男性とシス女性のカップルで、トランス男性の法律上の性別が女性のままの場合、「同性婚」の状態になってしまうため結婚はできない。しかし、中には法律上の性別を変更したくても、健康上の理由などから要件をクリアできない人などもいる。特例法の要件については緩和の議論が進んできているとはいえ、「結婚したければ法律上の性別を変更しろ」と言えてしまうのはあまりに暴力的だ。
④「国会で議論すべき」と司法の役割を放棄
東京高裁は、判決の前半で、国会で同性婚に関する法案が提出されても審議されていない点や、パートナーシップ制度が広がりLGBT理解増進法ができても、国は何も施策を進めていないことの問題を指摘している。この点について、公務員が「漫然と当該施策の実施を怠り」「不当な差別が生ずる状況を放置している」として、国家賠償法上の違法となる場合もあり得るとまで述べている。
しかし、ここまで言っておきながら、後半では「国会自体も、全体が立法に全く取り組んでいないという状況にはなく、質疑がされ、審議は開始されないものの、複数回、法律案が提出されている状況にある」などと国を擁護するような、正反対のことを言い出している。
「このままの状況が続けば、憲法13条、14条1項との関係で憲法違反の問題が生じることが避けられない」と釘を刺してはいるが、結論では「まずは国会で審議を尽くすべき」だという。しかし、おそらく国は今回の東京高裁の合憲判決を、より審議を進ませないための論理として使うだろう。
そもそも国会で「同性婚」をめぐる議論がまったく進まないから司法に訴えているにもかかわらず、「国会では審議されず国も施策を進めないけど、でも何も取り組んでいないわけではないから」などと言い訳を並べ、国会にボールを投げ返しているのは、三権分立や少数者の権利を守るという司法の役割・責任を放棄しているとしか言えない。何のために司法があるのだろうか。
⑤国におもねる裁判官の問題性
今回判決を下した東京高裁の裁判官は、3名とも裁判の途中で交代し担当となった人物だ。この3名の裁判官は、着任してからすぐに弁論を終結し、判決を言い渡している。控訴人らの生活の困難などについて正面から向き合ったのか大きな疑問を抱かざるを得ない。
さらに、東亜由美裁判長の経歴を見ると、3度検事を経験し裁判官と行ったり来たりしているようだ。こちらの記事では、東亜由美裁判官について「法務省大臣官房参事官、法務省行政訟務課長出身でいわば『法務省の弁護士』であり、判検交流の象徴のような人物である」とも指摘されている。国側の立場におもねることについて考えてしまう。
右田晃一裁判官は2年前、元北海道職員が同性パートナーの扶養手当を認められなかったことに対する訴訟について、札幌地裁の裁判長として請求を棄却する判決を下している。憲法判断も示さず「事実婚に同性間の関係は含まれないと解するのが一般的な解釈だ」と述べたという。
しかし、今回の東京高裁判決では、同性カップルは「事実婚と認められている」としており、言っていることが矛盾している。
判決の与える影響
この判決を書いた裁判官らは、これが世の中に出ることで、いま悩みながら生きている性的マイノリティの尊厳を奪い、抑圧し、生きる希望を踏みにじろうとしていることに、どれだけ自覚があるのだろうか。判決が助長するSNSやネットニュースのコメント欄にならぶ差別の言葉の数々が、人の命を奪ってしまうかもしれないことを、その重さをどれだけ認識しているのだろうか。
判決を読んで、少数者の権利を擁護するという役割を持つはずの司法の、裁判官としての矜持に疑問を持たざるを得なかった。
すでに札幌、東京一次、名古屋、大阪、福岡と5つの高裁判決では、明確な違憲判決がでている。とはいえ、今回の合憲判決が出てしまったことで、最高裁が合憲の判断を出しやすくなったのではないかという指摘もある。
一方で、たとえ高裁判断がすべて違憲であっても、最高裁が合憲を出す可能性はゼロではない。突然最高裁が合憲判決を出してしまう前に、あらかじめ高裁の時点で合憲判断が出たことで、弁護団は今回の東京高裁判決の問題点を主張できる。これによって最高裁に同様の論理を取らせないという対策を講じることができるとの声もある。
私自身、地裁では6件中5件で実質的に違憲判決が下され、高裁では5件連続で明確な違憲判断がだされている状況に対し、司法に対する楽観視のような意識があった。しかし、ここにきて東京高裁の差別的な合憲判断を前にして、最高裁がどのような判断を下すのか、改めてあらゆる可能性があることを痛感させられた。
来年2026年中には最高裁の判決が予想される。「いつか誰かが婚姻の平等を実現してくれる」のではなく、いま、一人ひとりが声をあげなければ実現しないこと、そのことについて考えながら、この文章を書いている。
すでに登録済みの方は こちら